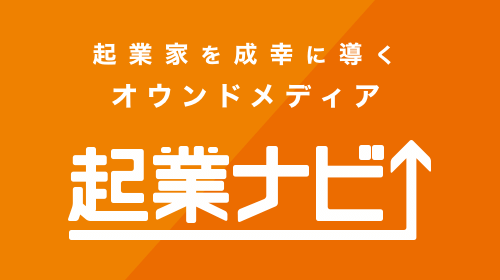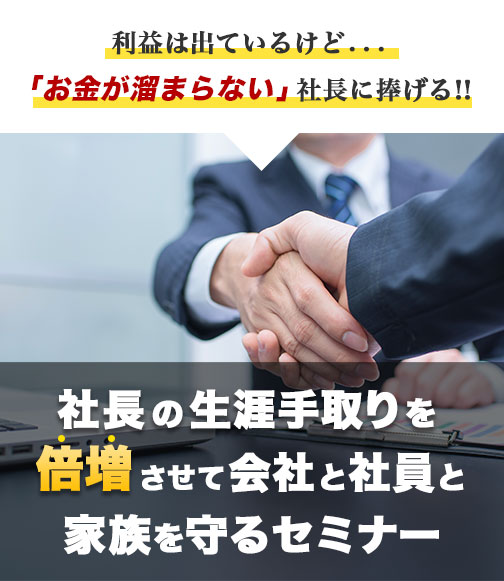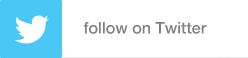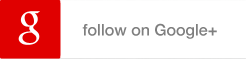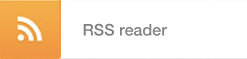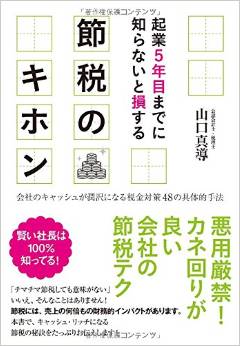私は公認会計士であるにも関わらず、財務諸表(決算書)が解ったと思えたのは、公認会計士になってから2年後くらいのある日でした。ある上場会社のキャッシュ・フロー計算書を作成しているときに、突然解ったのです。(ちなみに公認会計士になるためには会計士補(当時)になる必要があります。会計士補として就職してから数えると実に5年の月日が経っていることになります。)
恥ずかしくて申し分けない話ですが、当時は財務諸表(決算書)が理解できていないという認識もなく、解った気になって仕事をしていました。だから、財務諸表が読めない。決算書が解らないという経営者の方のお気持ちは、簿記や会計はカンタンだと主張する方達よりも理解出来ていると思います。
だいたいモノゴトをカンタンだという人の説明の方が難しいものです。だから、書店に置いてある本を読んで解らず仕舞いなのも解ります。
私は財務諸表(決算書)の理解は、かなり難しいと思います。
そう思っている私がその理解の仕方を書いたらお役に立てるのでは?というところが、この記事の発端です。
この記事を通じて、あなたが財務諸表(決算書)の世界の扉を開けて、その中に入って頂けるように説明していきたいと思います。